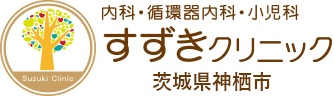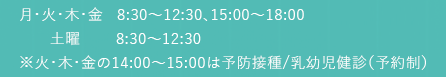肺炎マイコプラズマ
-2024年大流行の詳細と今後の課題-
昨年、2024年はマイコプラズマ感染症が全国的に大きな流行を見せ、多くの方が長引く咳や体調不良に悩まされました。
今回は、この一年を振り返り、マイコプラズマ感染症の基礎知識から流行の背景、そして私たちが得た教訓について、解説していきたいと思います。
知っておきたい!マイコプラズマ感染症の基礎
マイコプラズマ感染症は、「マイコプラズマ・ニューモニエ」という小さな細菌が原因で起こる呼吸器の感染症です。
風邪と似た症状で始まることが多いのですが、特に痰の絡まない乾いた咳が長期間続くのが特徴です。
どんな人に多い?
学童期のお子さんから若い成人に多く見られるのが特徴です。
マイコプラズマ肺炎の患者さんの約8割は14歳以下であり、中でも7歳から8歳のお子さんが最も感染しやすい年齢層です。
どうやって感染するの?
マイコプラズマ菌の増殖はゆっくりで、感染するには比較的近い距離での飛沫感染が主な経路と考えられています。
感染した人が近くで激しく咳をし、その飛沫が直接相手の気管支の粘膜に到達するような、かなり近い距離での濃厚な接触が必要と考えられています 。
症状は?
初期症状は発熱、倦怠感、頭痛などで、風邪と区別がつきにくいことがあります。
その後、特徴的な乾いた咳が出始め、解熱後も数週間続くことがあります。
肺炎を引き起こすことは比較的まれですが、重症化する場合もあるため注意が必要です。
2024年、なぜこんなに流行した?
過去には、1980年と1984年のオリンピック開催年にマイコプラズマ肺炎が流行したことから、「オリンピック肺炎」と呼ばれることもありました。
しかし、1991年にマクロライド系抗菌薬であるクラリスロマイシンが登場してからは、流行は比較的落ち着きました。
ところがその後、このマクロライド系の薬に対して抵抗力を持つ菌(耐性菌)が出現し、2012年に耐性菌による流行が起こりました。
2016年にも流行があり、やはり耐性菌の割合が高い状況でした。
2020年はコロナ禍でソーシャルディスタンスなどが普及し流行がありませんでした。
その後感染症対策の緩和に伴い、人の往来が増えたことが、2024年の流行の一因かもしれません。
またマイコプラズマは終生免疫はありませんが、4年くらいは免疫力が保たれるのが周期的に感染を繰り返す原因という見方もあります。
検査と治療の現状
マイコプラズマ感染症の検査には喉の奥を拭う迅速抗原検査がありますが、マイコプラズマはより深い場所に存在することが多いため、感度は約80%とやや低めです。
より正確な診断には、血液検査やPCR検査が行われますが、結果が出るまでに時間がかかることがあります。
治療の基本は、マクロライド系の抗菌薬です。
マクロライド系の薬を投与すると、発熱期間や咳が続く期間が短縮し、気道に存在するマイコプラズマの菌の量が減少することが確認されています。
しかし、耐性菌の問題があるため、症状が改善しない場合は他の種類の抗菌薬が検討されます。
特に小さなお子さんの場合は、早期の適切な治療が重要です。
大人の場合は?~抗菌薬の使い分け~
若い成人の場合、マイコプラズマ気管支炎は自然に治ることもあります。
そのため、安易に抗菌薬を使用すると耐性菌を増やしてしまう可能性があるため、慎重な判断が必要です。
症状が軽い場合は、抗菌薬を使わずに経過観察となることもあります。
厚生労働省のホームページにも、成人の軽いマイコプラズマ気管支炎に対しては、必ずしも抗菌薬を使用しないという治療方針が示されています。
2024年の流行から私たちが学ぶこと
今回の流行を通して、マイコプラズマ感染症は決して油断できない感染症であることを改めて認識しました。
特に、長引く咳には注意が必要です。
そして、抗菌薬の適正使用の重要性も再認識されました。
過去の2012年、2016年の流行の際は、耐性菌が問題となりました。
本来効果があるはずのマクロライド系抗菌薬が効果なく、特にお子さんが重度の肺炎に陥る危険性がありました。
最後に
現在はマイコプラズマ感染症の流行は落ち着いていますが、今後数年後に再び流行する可能性も考えられます。
その際には、若い成人の患者さんに対して抗菌薬を処方するかどうかは、患者さんの症状の程度や意向を十分に踏まえながら、慎重に判断していく必要があると感じています。
耐性菌の問題を踏まえると安易な抗菌薬の使用は避けるべきであり、感染状況や患者さん個々の状態に応じた、より適切な治療戦略が求められています。

- インフルエンザ
- ノロウイルス感染症
- 甲状腺疾患
- 花粉症
- アレルギー性鼻炎
- 気管支喘息
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)
- 加熱式タバコについて
- 禁煙のすすめ
- 禁煙外来
- 抗菌薬(抗生物質)の乱用予防について
- 高齢者肺炎球菌ワクチン

- 高血圧
- 減塩のすすめ
- 不整脈
- 不整脈をどう見つけるか
- 心房細動
- 心不全
- 大きく変わった心不全治療
- 狭心症
- 弁膜症
- 脂質異常症(高脂血症)
- 糖尿病
- 高尿酸血症(痛風)
- 静脈血栓塞栓症
- 大動脈弁狭窄症
- B型ナトリウム利尿ペプチド(BNP)について

- 手足口病
- 突発性発疹
- 咽頭結膜炎(プール熱)
- おたふくかぜ
- みずぼうそう
- アトピー性皮膚炎
- 食物アレルギー
- ワクチンについて
- 注射の痛みを軽減する方法